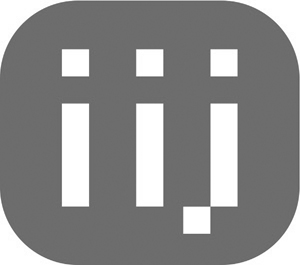- Text
- Review
JCDデザインアワード2011審査評
このアワードは、デザインの、それも空間の、それも構築される建築というよりも、生活に身近な現象的空間に焦点を合わせている。 50年ほど、そうしてやってきた(JCDは50年を経過したのだ)。公募されるデザインのその時々の評定にすぎないのだが、その時々の、とすましていいのだろうかと考えたことがある。特に1995年以降、おおむね5年が経過すると特徴的な現象が現れ、やがてそれは次の現象に移る。世間の流行の反映もあるし、経済のドタバタも要因として現れる。
ゼロ年代、日本は不況で、リーマンショックもあり、商環境デザインジャンルは大変だった。アワードも予算の豊富な案件が減り、建築家を任じるデザイナーからの応募が急拡大した。そこに現れるデザイン感覚にも変化が生じた。あれほど隆盛した飲食店舗の応募は終盤激減した。そのようにして、季節が循環し、新しい動向が芽生え、めでたくアワードの公募に結実する。そう待ち構えていられればいいのだが、さすがにそれは無理だ。そんな気分を引っ張りながら公開審査会場に臨むのだが、この気分はおそらく私一人ではない。普通にこの業界で15年20年ほどを経験していれば同じような気持ちをどこかにもっているはずだ。何か。
何かがとっくに変わっている、ということだ。われわれの産業のことである。明治維新以来の第一波の近代化、それにともなう縦割りの領域文節作法、その結果としてわれわれの職能の分断(インテリア、ディスプレイ、サイン、建築……)、そして、戦後の第二波の近代化=アメリカというパラダイム下の消費と拡張。どうもそれらが変わった、と感じざるを得ない。デザインアワードという社会の毛細現象にも、それらは押し寄せてきているのだ。JCDデザインアワードのゼロ年代の推移は、終わりつつあることへのトコロテンのような押出しと言えなくもないのだ。
2011年の公募は3.11の直後だった。アワード開催の可否も検討されたが、杞憂だった。410点の応募作品の中には海外からの応募もあり、変わろうとすることの片鱗が散見された。海外勢を除けば、われを競うという風情は皆無。その中で小降りでもパワフルという、MINIクーパーのような「レッドライト・ヨコハマ」が大賞を得た。
JCD理事長
JCDデザインアワード審査委員長
飯島直樹
年鑑日本の空間デザイン2012 / 六耀社
Copyright IIJIMA DESIGN. All rights reserved.