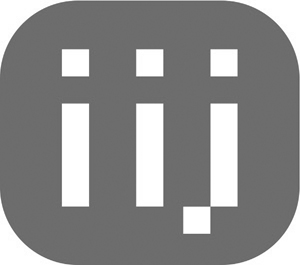- Text
- Bibliography
- 1969年の問いかけ「我々とは何者か」
古い話で恐縮だが、1969年発行の「デザイン批評」季刊第10号という雑誌を持っている。今ならあり得ない過激な図柄のイラスト(横尾忠則)が表紙を飾り、硬い文章がびっしりと中を埋める。そうそうたる執筆者がデザインレビューで時代に切り込む、過激なカウンターカルチャー雑誌の趣だった。この号では、なんと日宣美紛争の支援が特集されている。
1969 年夏、大学キャンパスをバリケード占拠した武蔵美(ムサビ)や多摩美の学生たち数十名による「日宣美粉砕闘争」が勃発した。グラフィックデザイン界のステータスゲートと化した日宣美賞の審査会場に 40~50人のヘルメット姿の学生が押しかけ、結果的にこの賞を潰してしまったのだ。デザイン界の大事件だった。田中一光、亀倉雄策、福田繁雄、木村恒久、和田誠、そして10号の責任編集者粟津潔も日宣美審査員側にいた。そんな面々を前にして、後年イラストレーターとなる知人の故三嶋典東は学生側にいた。1968 年のカンヌ映画祭を占拠し中止させたゴダールやトリュフォーのように、黒いヘルメット越しに日宣美粉砕を迫ったらしい。フリーランスのデザイナーたちは賞の維持に拘泥することなく「そんなにお前らが日宣美の危機を言うのなら」と、あっさり日宣美賞をやめてしまったのである。
「デザイン批評」に掲載される学生側の論と筋立ては、現在ではとても理解できるものではないだろう。社会のあらゆる問題を資本主義的矛盾に差し向け、無茶な「造反有理」をデザインに放り投げ、日宣美の権威化したデザイン界を「自己否定」する闘争だった。
50年も前のことだが、日本のグラフィックデザイン界はこうした「デザインの問いかけ」を経て現在のJ AGDAに至っているのだとあらためて思い知る。
日宣美を問いかけたヘルメット姿の学生はすでにいない。しかし「デザイン批評」が問いかけた「日宣美からデザインを奮還できるか」や、巻末の投稿欄「造反」に武蔵美で粟津潔の薫陶を得ていた若き谷口正和が投稿した「日宣美に今何が問われているのか」は、今でもデザイン賞を主催する側にとって不断の問いかけ、「我々とは何者であるのか」の問いかけであるだろう。
この問いかけは私たちの『年鑑日本の空間デザイン』への問いかけにもつながるように思える。日宣美と同じ時 期に、商環境、ディスプレイ、サインといったそれぞれのデザインカテゴリーの振興を目的にデザイン賞が設立され、それがある時期に年鑑というメディアを介して合同したのが『年鑑日本の空間デザイン』である。記録媒体としての年 鑑であればそれで十分だろう。でもはたしてそれだけでいいのか、と刊行に向けて集まる団体有志が合同の議論の 場面を構想した。2005 年設立の空間デザイン機構である。
年鑑のタイトルの「空間デザイン」を共有する我々とは何者なのか。69年の日宣美のような過激な問いかけではないが、年鑑刊行を介した空間デザイン機構の場においてそんな問いかけがあったのである。杉本貴志から川久保玲に至る6 回の非公募「KU/KAN 賞」贈賞は、空間デザインの多様性を包摂することへの問いかけでもあった。2019 年に起きたJCDとDSAのアワード統合という大きな動きもまた、空間デザイン界への「我々とは何者なのか」の問いかけであるように思う。
現在の COVID-19 は、自然と人為の間を蹂躙して、 人間に「自分たちは何者であるのか」を突きつけた。こうした時期に、1969年の問いかけはあらためて再考すべき課題ではないだろうか。
飯島直樹デザイン室
飯島直樹
年鑑日本の空間デザイン2021 / 六耀社
Copyright IIJIMA DESIGN. All rights reserved.