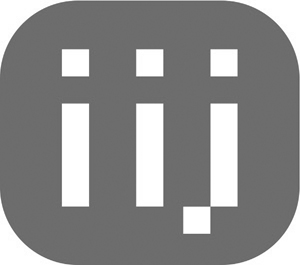- Text
- Bibliography
聴診器:1984年1-12月に商店建築で連載したインテリアデザイン批評のコラムページ
メンバー:沖健次/渡辺妃佐子/榎本文夫/青木淳/平川武治/飯島直樹
1984.07/テーマ:デザイナー論
- 近藤康夫_飽くことなき反復
ときに硬直した身振りで、ときに軽やかな足取りであったりしながら、Kが次に見せる表情は常に前のつづきなのだ。それは、よく似た手口といったものでもない。似ているのではなく、同じ物語のつづき、もしくは反復なのだ。Kは、ひとつの物語を反復して語りつづけているのだ。だから、Kにとっての新たな仕事は、その物語を終結させることよりも、ひたすら延命させるためにあるかのようであり、それは作家のアイデンティティとかの牧歌的な構図の外で、むしろ、かたくななまでの作法にのっとって為される。Kの作法
物語のはじまりは一件の小さな店舗である。同時にKの代表作といっていいくらいに、Kの作法の原型が、ここに集約している。ジョゼッペ・テラーニの幻の計画「ダンテウム」を彷彿とさせる列柱と、半透明のガラス・スクリーンが店舗を構成するための機能の分節、空間の分節の役割を果たして内部空間に組み込まれている。服の販売の店であるにもかかわらず、店頭に置かれるべき商品を、半透明のガラスの向こうに押しやり、そのガラスに沿って屹立する列柱で囲われた、床面積の半分以上を占めるスペースは、文字通りスペースで何もないという、極めて大胆な構成である。もちろん、こういった構成は欧米の店舗の販売方法によく見受けられるもので、格別刺激的なものではない。Kがここで刺激的に物語っているのは、その特異な店舗の用いられ方を可視的な構造に置き換える際の空間把握の仕方である。
この店では、物体(フォルム)としてのありようや素材感のインパクトに寄りかかるのではなく、そうした要素相互の関係づけにデザインのエネルギーのほとんどがそそがれているように見える。そして、そうした関係づけが、内部を所与のものとして抽出した上で、もうひとつの内部を積極的に分節するという手法で為されている。内部に内部をもう一度建築するわけだから、Kの目論む内部は、いわば「隠喩としての建築」といっていいかもしれない。K自らの言う「内部空間の再構築」は、空間の一次構造(たとえばインテヂアデザインの場合、与えられた室内)に、第二、第三の構造を見出してゆくプロセスであり、それは最早、内部のサーフェイスというよりは形式的な操作(主に柱と梁)による建築のメタファーである。この内部の建築化の主題は、それぞれに表情のちがいはあるにせよ、現在に至るKの仕事に飽くことなく反復する。Kにとっては作法のようなものなのだが、繰り返していえば、その作法はKの作風の持続のためにあるのではない。そうではなく、たとえば茶道の作法のようにKの外にあって、その都度Kをかきたてる、かたくなな何者かなのだ。
意図的なリファレンス
では、こうした作法にのっとったKのデザイン言語が目新しく斬新なのかといえば、そうでもない。逆に、目新しいものは何もない。過去の事例で参照可能なものの分布と散布といったら言い過ぎだろうか。だが、あらゆるデザイン言語が開発されつくした後の、むしろ意図的なリファレンスといえなくもないのだ。あらゆる言語は、言語についての言語である。日本建築の架構法に身をあずけ、テラーニのファッション的機械を擬似体験し、ときにアイゼンマン風の構造分析をオードブルにしては、Kは、ひたすら近代が作りあげてきた言語をパラフレーズしているかに見える。われわれの前に次々と立ちあらわれる作品が、ストイックで生真面目に見えれば見えるほどアイロニカルな容貌を伴ってくるのはそのためである。百花繚乱の最新デザインが混然とした風景を作りあげている商業施設の環境の中ではなおさらである。
聴診器 / テーマ:デザイナー論 / 商店建築 / 1984.07
Copyright IIJIMA DESIGN. All rights reserved.