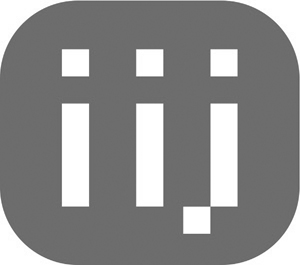- Text
- Bibliography
- 「60年代ラジカリズムとジョエ・コロンボ」
60年代の異議申し立て
70年代はじめに雑誌「美術手帖」に連載され、その後出版された磯崎新の「建築の解体」は、モダニズムへの異議申し立てを読み解くための海図のような本である。最前衛の建築家達が紹介されるのだが、その中に唯ひとり理論研究者が含まれていた。1965年に「都市はツリーではない」を著したクリストファー・アレグザンダーである。都市の現実は一本の樹のように幹から徐々に枝分かれする計画的形式ではなく、もつれた網のような不確定で多様な「セミ・ラティス」構造であるとして、計画としての都市デザインに異議を申し立てた。60年代の異議申し立ての、羅針盤のような論文だ。
60年代は、アメリカの批評で60年代のマニフェストといわれたスーザン・ソンタグの「反解釈」や、シンプルモダンなグラフィックデザインに牙を剥いた日本の横尾忠則など、様々な領域で同時多発的にこうした異議申し立てが噴出した時代だった。インテリアデザインにおいても然り。洗練されたモダニズムに背を向け、むしろそのような美を廃棄するラジカルムーブメント(過激で急進的な動向)が沸き起こったのは1960年代のイタリアだった。
[ドムス]が教科書だった
筆者が入学した1969年頃の武蔵野美術大学のインテリアデザイン教育は、バウハウスから北欧モダンに繋がるモダニズムをバックボーンにしていたが、まったく興味が湧かなかった。その年、大学はバリケード封鎖で大荒れ(といっても日本大学や東京大学に比べるとセコイ)だったし、カウンターカルチャーの気分が蔓延して大学お仕着せのモダニズムはお呼びでなかったのだ。
世界の先端を意識し,我々の教科書となったのはイタリアのデザイン誌「ドムス(domus)」だった。「ドムス」は、20世紀の社会システムとそのイデオロギーたるモダニズムへの疑いがイタリアに先鋭化していたことを刻々と伝えていた。そしてその中で群を抜いて目立ったのがジョエ・コロンボだった。
セミ・ラティスのインテリア
例えば1965年の「ドムス」に掲載されたジョエ・コロンボによるアパートメントのインテリアデザイン。青と紫にあっけらかんと塗り分けられ、無機的な表層空間の中に居住行為を機械の部品のように装置化したSF的インテリアである。 LDK的な居住形式のツリーではなく、不確定で多義的な装置がパッチワークされるアドホックな空間は、インテリアにおけるセミ・ラティスの試みであり、1965年のアメリカのアレグザンダーとイタリアのコロンボに通底する「ラジカル」としても興味深い。
このインテリアデザインで特筆すべきは、デザイン王国イタリアにあって、デザインという行為の自己否定つまり「飾り立てる」デザインの拒否を表明したことだ。フォルムのデザインと思われがちなデザイン観からの離脱。そのアンチデザインの概念は、70年代の日本のインテリアデザインに大きな影響を与えることになる。
起点としてのジョエ・コロンボ
ジョエ・コロンボ(本名チェザーレ・コロンボ)はインテリアデザインにおける1960年代のラジカルムーブメントの先頭走者として、その後のスーパースタジオやアーキズームを牽引した。1962年から1971年まで活躍し41歳で夭折したが、短い期間に斬新なプラスティック素材のプロダクトや、実験的な居住空間を矢継ぎ早に発表した。
1969年の「ドムス」にはジョエ・コロンボのラブホテルのような居住空間の提案「ヴィジョネア69(VISIONA69)」と共に、透明アクリルのタワー状の家具「GIANT OBJECT」がひっそりと掲載されている。作者名はShiro Kuramataと記されている。この1969年の倉俣史朗以降、日本のインテリアデザインは世界への発信源となるのだが、ジョエ・コロンボは、先鋭たることにおいてその起点といえるだろう。
飯島直樹
NICHE 05 / 工学院大学建築学部同窓会NICHE出版会 / 2018.09
Copyright IIJIMA DESIGN. All rights reserved.