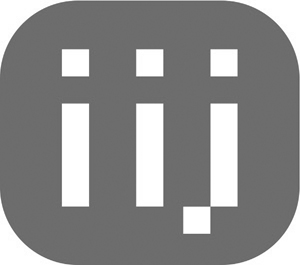- Text
- Bibliography
- インテリアデザインの発見
インテリアデザインの概念を定義づけるのは難しい。デザインのジャンルとしては建築の一部でありながら、工学の反対側で装い飾ることを得意としてきた。建築から見れば周縁「室内装飾」であり、戦後しばらくの時代はベレー帽を被った絵描きのオジさんたちの余技であった。
そんな室内装飾が「デザイン」として自覚されたのは1960年代だった。高度経済成長がインテリアデザインというジャンルを後押しする。デザインに従事する側もベレー帽を脱ぎ捨てて、デザインの一分野の職能として自覚するようになったのである。洗練された空間作りの方法。官能的な素材使いの習得。微細な照明のタッチを洗練。モダニズムも導入する。そんなインテリアデザイン観にまで成長していたといえよう。
ところが1960年代末に、そうしたインテリアデザイン観とは真逆のデザインが登場してしまうのである。それはインテリアデザインそのものを問い、自己言及するような、いきなりの革命だった。室内の意匠という見立てすら廃棄し身近な空間の「現象」とは何か。空間が「作動し機能する」こととはどういうことなのか、定常的な空間に隠れている「見えない空間」とはどんなものか。そうした、今書くと気恥ずかしくなるような問いかけが、夢想ではなく、収益を求められる商業空間を主な実験現場として投じられ実現した。
いきなりの革命の、先頭走者は倉俣史朗である。1968年という特異な時代と伴走し、日本の空間デザイン領域に、今日に至る大きな影響を残した。
1968年は20世紀の屈折点だと言われる。
政治社会的な変化としては1989年のベルリンの壁の崩壊(東西冷戦構造の終焉)の方が大きいが、その変化の前兆は1968年に胚芽していた。
無論能天気な学生だった当時の筆者に歴史の転換期の自覚など無かった。東大安田講堂とお茶の水界隈の催涙ガスの記憶、翌年の武蔵美での少々セコい大学紛争の最中で背伸びしたことだけは覚えている。何せ騒々しく、多くのことが身辺を行き交った。パリの5月革命の余韻、中国の文化大革命+ゴダールの「中国女」、三島由紀夫の切腹。美術手帖に建築家の論考が長期に連載(磯崎新の「建築の解体」)、難しい思想雑誌にはフーコー・ドルーズ・デリダの名前が掲げられていた。どうやらそれらの思想や観点はあらゆる表現領域の底のほうで影響し合い繋がっており、例えば写真表現の世界にも覆い被さっていることを知った(中平卓馬の「まずたしからしさの世界を捨てろ」)。川久保玲がモードの彼岸に立ち、コムデギャルソンを発進させたのも1968年である。
インテリアデザインも無縁ではなかった。それは収益を求められ制約が課せられられる商業空間において、先頭走者の倉俣史朗のデザイン作法を介して具体化したのである。倉俣史朗は、重力から自由になりたいと妄想した。重力のある建築的現実を不自由と感じた。インテリアデザインに現象する空間の現実は床・壁・天井である。そこからコトバを差し引くと、現実は意味を欠いた名付けようのない水平面と垂直面に還元できる。倉俣史朗は1960年代後半に、そこのところに単身乗り込んだ。内部空間を構築的な空間概念から解き放ち、皮膚や脳、身体や感覚から再編し、そこに独自の空間の捕まえ方を発見した。 そのひとつに表面/SKINがある。1969年「クラブ・ジャド」、1970年「マーケットワン」「エドワーズ」、1974年「四季ファブリック・ショールーム」、1983円「エスプリ香港」など。これらのインテリアデザインは、なかばサディスティックに、内部であることの空間の事実=囲われた表皮を自覚し、SKINであることに徹する。デザインがそのまま空間構造の自己言及であるかのような行為であり、アンチデザイン=装い飾ることの霧散である。そんなものを驚くことに実際の商業空間に投入したのである。
こうしたアプローチは、それまでの装い飾る観点からインテリアデザインの領域を大きく解き放った。独自のデザイン言語がここから生み出された。たとえば倉俣に続く世代、杉本貴志のルーバーを多用した「表面生成のデザイン(1970年代)」は今日の隈研吾の粒子の空間、「負ける建築」にも連なり、現象学的方法として継承されている。 日本のインテリアデザイ界は1968年以降いくつかの変化を経験する。バブルの時代の表現過剰な時期。90年代の鎮静とアトモスフィアデザインの巻き返し。ゼロ年代の身体と空間の測定であるかのようなアフォーダンス風姿勢など。だがそれらすべてに、1968年とその季節に発芽した「デザインの発見」が及んでいる。日本のインテリアデザインを顧みるときに、これは何度も立ち返って記憶すべきことだと思う。
インテリアデザインの半世紀 / 六耀社 / 2014.03
Copyright IIJIMA DESIGN. All rights reserved.