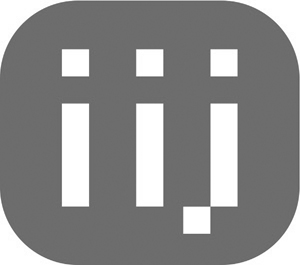- Text
- Bibliography
- 余話
_JCDデザインアワードの体験
JCDデザインアワードという空間デザインの賞の審査にかかわっている。他人のデザインをあれこれ評定することなど、できればしたくない。普通はそう思うだろう。私も同じだ。大賞以下の序列の根拠を示せと言われたら大層困る。可否の絶対基準などないから、審査には未知を発見するドキドキ感と同時に、判定根拠不確実なドギマギ感が常にある。
このアワードは社団法人日本商環境設計家協会という団体が主催する。1974年に公募を始めたので結構歴史があり、日本の世相の変転にも相応しながら実行されてきた。協会名に明記されるように、賞の対象は主に商業空間やインテリアデザインの領域である。消費社会が拡大した70年代の百貨店の隆盛を背景に、職能ジャンルとして大きく開花した。続く80年代の過剰な揺籃期には、地方都市に乱立するファッションビル、ショッピングセンターが猛スピードで消費された。DCブランドからカフェバーまで、華々しい空間プロデューサーが登場し、デザイナー諸氏は海外にまで押し掛けた。この方面のデザイン領域は、80年代はまったくもって慶賀至極であった。そしてこの頃、社会的にも「空間」はおおいに着目されたのである。
しかし1990年代に大きく変化する。断頭台のようにガチャンと音を立ててバブルが終わった。シャレたカフェバーは一掃され屋台村が日本中に出現した。怒涛の不景気が当たり前の風景となり、循環するであろう景気回復が幻想であると気づく90年代中頃になると、このアワードを受賞するデザインのタイプが大きく変わったのである。それは今振り返れば、現在の空間デザインの様々な特徴、あるいはゼロ年代の現象につながる「兆し」であったように思われる。
「兆し」のひとつは1994年の商環境デザイン大賞、妹島和世の「パチンコパーラーⅠ&Ⅱ」だった。デザインの大賞がパチンコ。デザイナーは繊細な若手女性建築家だった。専門家しか知らないコワモテな建築の前衛=ムズカシイ感覚、が欠落する。軽やかであっけらかんとしたデザインだった。だからといってポップな軽さだけでもない、その頃流行ったクエンティン・タランティーノ監督の映画『パルプ・フィクション』のアヴァン・ポップ(アヴァンギャルド+ポップ)が空間デザイン界に飛び込んできたような感じだった。そのときのデザイン賞委員長の内田繁が賞のあり方を改革し、1995年に名称を「商環境デザイン賞」から「JCDデザイン賞」に変えたことは、たんなる名称変更ではなかった。時代を抱え込むデザインの何かがその頃に大きく回転したことの「兆し」のように思えた。事実この時期を境に、この賞が招来するデザイン状況は、こんな言い方は大げさかもしれないが、国内外の世界を巻き込む社会構造の大きな変化に同伴して揺れ続けるのである。デザインだから文化面での揺れ、ではない。これは、社会背景、経済、時代の意識構造にまで入り込む大きな方位での揺れなのだった。
_世紀の変わり目
この本に登場する11人のデザイン作法は、その揺れにつながっているように思える。11人の内6人がJCDデザインアワードの受賞者であることを差し置いてもそう思える。どうしてそう思うのか。以下、少し長くなるが95年以降のJCD賞の軌跡について触れておきたい。
内田さんが実行した改変の一つは海外審査員の招聘であった(エットーレ・ソットサス、アンドレア・ブランジ、ガエターノ・ペッシェ、ジャン・ヌーヴェルなど)。招聘予算はゼロだから、友人関係が頼りで、たまたまの来日に審査員としてゲットする手法だった。インターネットが行き渡る時期であり、国内外という感覚が覚醒、コンピューターの浸透によりデザインの作法もメチャクチャ変わる頃だった。日本の95年の頃はオウム事件、阪神淡路大震災と社会の重苦しい捻転が露呈した。社会の現場が発する生々しい身体感覚と、事件や被害への皮膚感覚がデザインに波及しているように見えた。日本社会の日常に「オタク」が顕在化し、スーパーフラットがアート業界を席巻した。海外審査員も含めて“個性的な”審査員達(山本耀司、宮本亜門、糸井重里、原研哉、小山薫堂、など)はそんな時代に遭遇したのだった。
この頃の賞審査で、いったんは選外となった応募作をジャン・ヌーヴェルが「これしかない!」と探し出しダダをこねた結果、急遽[ジャン・ヌーヴェル賞]をねつ造したのが98年だった。震災によって“全壊”認定された自宅をコケの一念で”全快”し、自らの仕事場とした宮本佳明の「『ゼンカイ』ハウス」である。デザインの出来具合ではなく、震災が生む、建築の存在意思そのもののようなイメージの強度こそをジャン・ヌーヴェルは評価したのだが、この賞をめぐる揺れ、つまり「どこがいいの?」「これのどこがデザイン?」は、その後に様々な影響を残した。2001年のJCDデザイン賞で大賞を受賞した京都の極小バー「プレストプニク」に至っては、それは騒動にまでなった。デザインは京都在住の若干24歳のデザインユニット(当時はユニットが流行した)14SDの林洋介と北村卓也の若者二人。チープな内装でカウンターのガラス下の砂がグラスの磁力に呼応するといった不思議なバーであった。形の付与というより時間の痕跡に反応しようとする「様相」をテーマとするデザインだった。私はこのとき審査員ではなかったので難を逃れたが、審査員は大変だったはずだ。各方面から「何で、なの?」光線が打ち込まれたからである。私はといえば、この次第は結構おもしろいのではないかと眺めていた。そしてこの受賞結果に興味を覚え、14SDの二人にも京都で会ったりした。このときに感じたことは、その後の2000年以降のJCDデザイン賞に出没するゼロ年代のデザイン動向にも等しく感じることであり、おそらく今回の11人の、デザインとか建築とか名付けようのない“様子”にも連なる感覚だと思う。
90年代の中頃は一方で、インテリアデザイン界に特徴的な状況が生まれた時期である。ミニマルで禁欲的なハイデザインが東京を中心とするインテリアデザイナーの主流だったのだが、この頃、俄かに大阪方面から過激で騒々しい感覚的なデザインが大量に勃興したのである。戦国時代の軍団を思わせる一気呵成の勃興だった。森田恭道、間宮吉彦、辻村久信、文田昭仁らの関西の面々である。主に飲食店のデザインでその動向は発揮され、大阪の南船場のように街全体の風景を変えるほどの勢いとなった。その場でしか成立しない空気感、アトモスフィアを身上とするデザイン作法が特徴だった。
JCDデザイン賞はこのような動きを経験する中で、ゼロ年代に海外への公募、ネット応募など改変を進めた。2006年にJCDデザインアワードと名称を変え、今日に至っている。商業という過酷さをバックボーンにその時々のリアルと直結するので安定した定位置がない、そういう宿命のアワードであり、近年に至って空間デザイン領域におけるまことに奇妙な現象「ゼロ年代現象」を経験することになるのである。
_ゼロ年代現象
「ゼロ年代現象」は、ある日、勝手に、ドカドカと押し入ってきた。そういう感覚だ。2000年代の真ん中頃、どういうわけかJCDデザインアワードに大挙して建築家を標榜する、しかも相当に若い人たちが応募するようになったのだ。そして大挙して受賞した。nendoという意味不明な応募者(佐藤オオキ)から始まったような記憶がある(京急立会川駅近くの川岸に立つ、内外を布でカバーしたクリストのような極小フレンチレストラン「canvas」)。その後ドドっと押し寄せる。中村拓志、KEIKO+MANABU(沢瀬学+内山敬子)、長岡勉、大野力、迫慶一郎、米正太郎、寶神尚史、平沼孝啓、NOSIGNERほか。もちろんこの本の登場者も。長坂常、トラフ(鈴野浩一、禿真哉)、岡部修三、中村竜治、遠藤幹子。奇妙な風景であった。それまでのJCDデザインアワードの応募反応者はその方面の専門家であり、建築家はたまに「商店を作ったから」の応募だった。ところがゼロ年代の建築畑の若手は、空間種別規定の代わりに「買うこと」「食べること」「集うこと」「楽しむこと」「遊ぶこと」果ては「感じること」まで、空間の様子を列挙する少々奇妙なデザインアワードに到達したのだった。その結果、従来は浮上しなかったような物件が日の目を見たのである。応募作のほとんどはチープ。小さく低予算で80年代には皆無の案件がずらっと並んだ。そして上位の受賞者のみならず、世間の高額なプロジェクトを押しのけて大賞までを席巻した。ギョーカイはびっくりした。各方面のデザイン、建築雑誌、海外のメディアまで取材を要請してきた。慣れない光景に、国内のギョウカイではまたもや「何で?」が発せられた。
空間のデザインというフィールドにとって、ゼロ年代というのは大変興味深い対象だ。記録しておかないとすぐに忘れてしまうのがこのギョーカイである。そんな気持ちもあり、この『ゼロ年代11人のデザイン作法』の刊行を手伝うことになった。10年位の間に推移したゼロ年代の空間デザインの背後を、しかも当事者本人の肉声で聞いてみたい、というのが私の個人的モチーフである。
参集した11人の選定理由は「カテゴライズに困る」ヒトタチである。そして、ゼロ年代の中でも若い世代だ。全員に言葉を強要しつつ、理解というよりは想像の共有を図りたいと思った。また、このゼロ年代の風景は日本以外の場にもリンクし得るだろうと、ソウルのリム・テヒにも参加願った。加えて、批評が激無なこのギョーカイに火を点そうと、デザイナーにして批評を開始した浅子佳英も加わった。
_間主観性
11人の一人一人への興味は、直接そこのページを参照されたい。
一つ、感じたことがある。長坂常の仕事場「HAPPA」に集まり、一夜雑談をしたことがあった。禿真哉、鈴野浩一、岡部修三、柳原照弘、長坂常、そしてジャーナリストの新川博己。それぞれの今やっていること、3/11の経験などの対話となった。
途中で、私は「あれ、なんか懐かしい感じだな」と思った。それは彼らが進めつつあることの共通の姿勢のようなものだ。弱さのようなもの。主体がエラいという感覚の欠如。主体が主観をもって世界を捕まえるのではなく、客体との溶け合いの最中にリアリティを探り出そうとする姿勢。デザインの対象をそのように包含しようとする気持ちが共通に感じられ、それを懐かしいと思ったのだ。
長坂常の「HAPPA」の空間、廃材テーブルをエポキシで固めて再生するデザイン。「向こうからやってくるものを受け止める」感覚。岡部修三の最初の仕事だった「レコード屋」。客の主体と店という客体の対置を中間化しようとする、野球部体育会系の、デザイン上のしなやかな意思。家具の部材を、デザイナーの主観から解き放ち物そのものが本来持つ流動的流れに押しやる、今時珍しい物派デザイナー柳原照弘。話し方のスタイルが何よりも「間」にあり、ショップ空間から家具、生成そのもののような舞台装置が、常に“間”に偏在する感じのトラフ。
懐かしいと思ったのは、1968年頃に大変流行した「現象学」というムズカシイ思想の「間主観性」という概念にそっくりだからだ。その頃の先端を走った多木浩二、森山大道、中平卓馬達の同人写真雑誌「PROVOKE」の思想的バックボーンは「現象学」であり、表現の指針となったのが多分「間主観性」(とりわけメルロ・ポンティの『眼と精神』)である。主観の思い込みを唾棄し「まずたしからしさの世界を捨てろ」がスローガンだった。主観の唾棄は20世紀を通じて反復するテーマ(20世紀初頭のフォルマリズムや中頃のアメリカにおける抽象表現主義)なのだが、写真であれば写真表現者の主観ではなく、写真の対象となる客観との間の「関係」こそが主題なのだとアジテーションした。主観の思い込みはクソの役にも立たぬ、そんな幾分パセティックな物言いだった。
今、私は勝手に想像を楽しんでいるだけなのだが、この「間主観性」の気分、何やらゼロ年代の諸氏のそっけなさに通底する気がしないでもない。まさか「まずたしからしさの世界を捨てろ」のアジテーションではないと思うが、この本によって、そのそっけなさが何処に向かおうとしているのか、想像の共有が図れれば望外である。
ゼロ年代 11人のデザイン作法 / 六耀社 / 2012.01
松原慈 有山宙 / 井手健一郎 / 遠藤幹子 / 岡部修三 / 鈴野浩一 禿真哉 / 長坂常 / 中村竜治 / 柳原照弘 / リム・テヒ
浅子佳英 / 飯島直樹
Copyright IIJIMA DESIGN. All rights reserved.